英語には同じような日本語訳の単語がたくさんあり、どちらを使えばいいか悩みますよね。
例えば今回紹介する、「Bring about」と「Cause」も訳が似ており、使い分けるのは苦労します...
そんな悩みを解決するため、このサイトでは「Bring about」と「Cause」の違いが「だれでも分かるぐらい簡単に解説」します!
「*信頼できる内容を提供するため、ネイティブに内容を確認して作成しています。」
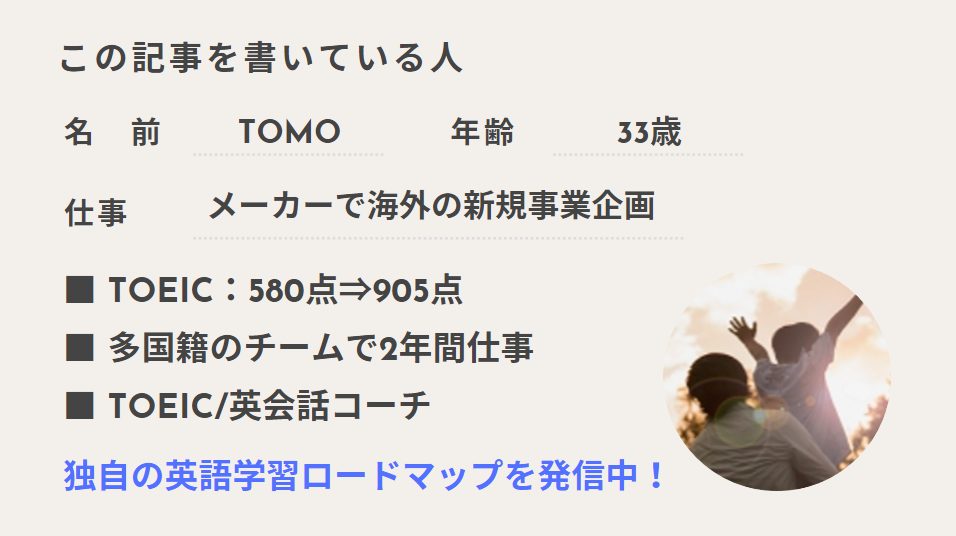
まずは「Bring about」と「Cause」の違いについて1分で理解しよう!
「bring about」と「cause」の違いを説明します。
bring about(引き起こす)は、何かを実現させる、あるいは結果をもたらすという意味を持ちます。
一般的に積極的な行動や過程に寄与するニュアンスがあります。
例:We hope to bring about positive change in the community.
(私たちは地域社会に良い変化を引き起こしたいと思っています。)
一方、cause(原因となる)は、ある特定の結果を生じさせる原因を指します。
無意識的または自然なプロセスを含むことが多いです。
例:The storm caused widespread damage.
(その嵐は広範囲にわたる被害を引き起こしました。)
ネイティブスピーカーは「Bring about」と「Cause」をどのように使い分ける?
bring aboutは「何かを引き起こす」という能動的なニュアンスが強く、特定の目標や意図に基づいて変化をもたらす時に使われます。
例文:The new policy will bring about significant improvements in the education system.
(新しい政策は教育システムにおいて重大な改善をもたらすでしょう。)
一方、causeは「結果を生じさせる」で、通常は既存の条件や状況がもたらす自然な結果を表す時に使われます。
例文:Allergies can cause breathing difficulties.
(アレルギーは呼吸困難を引き起こすことがあります。)
「Bring about」と「Cause」の使い分けが難しいケースと解説
(1) 「The government caused a lot of changes in the economy.」と「The government brought about a lot of changes in the economy.」
- causeの場合:政府の行動が変更をもたらしたが、それが意図的かどうかは明確ではない。
例文:The government caused a lot of changes in the economy due to the pandemic.
(政府はパンデミックの影響で経済に多くの変化を引き起こしました。)
- bring aboutの場合:政府が積極的に変化を促進した印象を与える。
例文:The government brought about a lot of changes in the economy through its new fiscal policy.
(政府は新しい財政政策を通じて経済に多くの変化を引き起こしました。)
「Bring about」と「Cause」の類義語とその使い分けについて
- produce(生じる):何かを創出する場合に使います。
「bring about」と似ていますが、より広範囲の文脈で使われるため、意図や過程を必ずしも含まないことがあります。
例:The factory produces thousands of goods every day.
(その工場は毎日数千点の製品を生産しています。)
- generate(生成する):新たなものや結果を作り出すことを指しますが、主にエネルギーや信号の生成に使われがちです。
例:The plant generates electricity from solar energy.
(その発電所は太陽エネルギーから電力を生成しています。)
「Bring about」と「Cause」の発音をマスターしよう!
- bring about(ブリング アバウト):/brɪŋ əˈbaʊt/ 発音のポイント:最初の「bring」は「ブリング」と聞こえ、次の「about」は「アバウト」と発音します。
カタカナ読み:ブリング アバウト - cause(コーズ):/kɔːz/ 発音のポイント:「cause」は「コーズ」とシンプルに聞こえます。
カタカナ読み:コーズ
「Bring about」と「Cause」をフォーマルな場面で使うならどっち?
フォーマルな場面では「bring about」を使うことが多いです。
特に政策や計画に基づく変化を述べる場合、「bring about」は積極的なアプローチを示唆し、ポジティブなニュアンスを持っているためです。
例えば、ビジネス会議や学会での発言では、「bring about」が好まれることがあります。
「cause」はより自然な原因によって生じる結果を表すので、論文などの実証的な話題で使われることが一般的です。
「Bring about」と「Cause」の違いについてよくある質問(Q&A)
Q1: 「bring about」と「cause」を混同するとどうなりますか? A: 文脈によっては誤解を招くことがあります。
「bring about」は意図的な変化を示唆しますが、「cause」は受動的な状況を示すため、使い方を間違えると意図が不明瞭になることがあります。
+α 結局英語を学ぶのはオンライン英会話が最短!
私も英語学習を始めて15年以上がたちますが、結局英語をマスターする最短の方法はオンライン英会話という結論に至りました。
オンライン英会話については以下の記事でも紹介していますので、是非参考にしてください!
オンライン英会話はどれがおすすめ?徹底解説
[発音マスター]ネイティブとの徹底指導で最短で発音がマスターできるオンライン英会話
[海外旅行を楽しむ]海外旅行前の英語学習として最適なオンライン英会話


